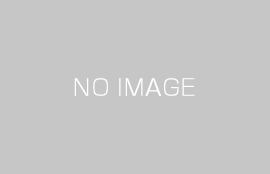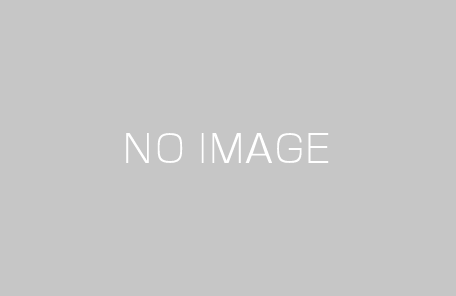2025年7月6日(日)
「コミュニケーションを」 永松 博
民数記9章15~23節(聖書協会共同訳)
「さて、ここに1冊の聖書があるとします。聖書自体は『情報』です。それが紙でできた本なのか、コンパクトディスクなどに入った電子図書なのか、といった媒体がなんであるかに関わらず、また書かれている言語が英語であっても、日本語であっても、その他の言語であっても、聖書自体はたんなる「情報」でしかありません。しかし、その聖書の内容について、たとえば教会で牧師や神父が説教をしたり、信者同士が語り合ったりすれば、その瞬間、聖書の内容は『コミュニケーション』のプロセスに同化して、時間と共に動き、人間の実人生に影響を与えうる存在になった、といえるでしょう。このように、『情報』と『コミュニケーション』は一見似ているようで、かなり異質な概念ではないかと思います」。9歳で失明し、18歳で聴力も失った全盲ろう者として、国内初の大学教授となった福島智さんの言葉です。民数記は、イエスの光を通してコミュニケーションされる神の像で読むこともできるかもしれません。
民数記は、エジプトで奴隷だった人たちが脱出し、難民となって一年が過ぎた頃から、四十年の荒れ野での旅を経てヨルダン川の東側まで至った経緯が語られる文書です。ちなみに、出エジプト以降の最初の1年間のことは、出エジプト記が伝えています。人びとは46日目にシナイの荒れ野に至り、さらに三日後の49日目には十戒の石板を授かります(出エジプト記19章)。この十戒の石板授与の出来事は、上述した福島智さんの視点で言えば、いわゆる神による戒めを伝える「情報」伝達とも言えるかもしれません。また、出エジプトから1年ごろ、人びとは移動式テント礼拝施設「幕屋」を組み上げました(出エジプト記40章)。幕屋が完成したときの出来事は、出エジプト記40:34~38にある通り、きょうの箇所と重なっています。神が共にいることをあらわす雲や火が幕屋を覆い、人びとは雲や火と共に行動したとの記述です。ここには、単なる「情報」伝達でとは違うやり取りとしての「コミュニケーション」があるのを感じます。神は、雲や火を通して、人間の実人生に影響を与えうる存在としてあったということです。
荒れ野にいた人びとは、まるで無重力で真空の宇宙に放り出されたように、上下右左も分からず、真っ暗、真空無音の中で、絶対的な孤立感を感じていたかもしれません。そのような中で神は、新たなファラオ的唯一絶対的支配者となって戒めを伝達し、契約を結んで雲や火で導いたのでしょうか。むしろ、他者の存在を必要とする幼子イエスを通して読み直すならば、神はコミュニケーション相手としての他者を求めておられたのではないでしょうか。光そのものに明るさはなく、光を反射する「何か」があって、初めて光は明るさを生み出します。「生命は/自分自身だけでは完結できないように/つくられているらしい/生命は/その中に欠如を抱き/それを他者から満たしてもらうのだ」(吉野弘「生命は」)求め満たす関係により、生きられます。