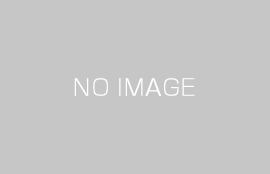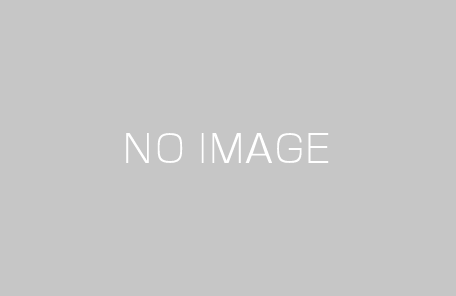2025年7月27日(日)
「荒野の四〇年×二=戦後八〇年」 永松 博
民数記23章1~12節(聖書協会共同訳)
カナンの地偵察後、民たちは、神を試み、聞き従わず、侮った罪で四〇年間荒れ野をさ迷いました。この歳月は、大きな罪に対する責任追及期間の目安、象徴です。
『荒れ野の四〇年』という有名な演説があります。ドイツ連邦共和国(当時の西ドイツ)のリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー大統領が、敗戦四〇周年(1985.5.8)に、民数記などを引いて行った国会演説です。「人間の一生、民族の運命にあって、四〇年という歳月は大きな役割を果たしております。…信仰の如何にかかわりなく、あらゆる人間に深い洞察を与えてくれるのが旧約聖書であり、ここでは四〇年という年月が繰り返し本質的な役割を演じております。イスラエルの民は、約束の地に入って新しい歴史の段階を迎えるまでの四〇年間、荒れ野に留まっていなくてはなりませんでした(申命記・民数記)。当時責任ある立場にいた父たちの世代が完全に交替するまでに四〇年が必要だったのです。しかし、ほかのところ(士師記)には、かつて身に受けた助け、救いは往々にして四〇年の間しか心に刻んでおけなかった、と記されております。心に刻んでおくことがなくなったとき、太平は終りを告げたのです。ですから、四〇年というのは常に大きな区切り目を意味しております。暗い時代が終り、新しく明るい未来への見通しが開けるのか、あるいは忘れることの危険、その結果に対する警告であるのかは別として、四〇年の歳月は人間の意識に重大な影響を及ぼしておるのであります。」(永井清彦編訳『ヴァイツゼッカー大統領演説集』岩波1995)
この国は来月8・15で戦後八〇年の節目を迎えます。「荒れ野の四〇年」×2の歳月です。これが負の重大な区切り目となることのないよう、神のみ心と歴史とを心に刻みたいと思います。また、バラムの姿は戦後第二世代以降を生きる私たちの役割を象徴しているかもしれません。バラムは、きょうの箇所で難民・移民を前に恐怖するバラク王のもとにいながら、「10私は正しい人々に連なって死にたい」と願い、王にではなく主に従い、神から授けられた祝福の言葉を語りました(11-12節)。ヴァイツゼッカー氏も、『荒れ野の四〇年』演説の最後には、若い世代へと向かいました。「われわれのもとでは新しい世代が政治の責任をとれるだけに成長してまいりました。若い人たちにかつて起こったことの責任はありません。しかし、(その後の)歴史のなかでそうした出来事から生じてきたことに対しては責任があります。われわれ年長者は若者に対し、夢を実現する義務は負っておりません。われわれの義務は率直さであります。心に刻みつづけるということがきわめて重要なのはなぜか、このことを若い人びとが理解できるよう手助けせねばならないのです。ユートピア的な救済論に逃避したり、道徳的に傲慢不遜になったりすることなく、歴史の真実を冷静かつ公平に見つめることができるよう、若い人びとの助力をしたいと考えるのであります。」神は、私たち一人ひとりにどんな言葉を授け、何を期待しておられるのでしょうか。